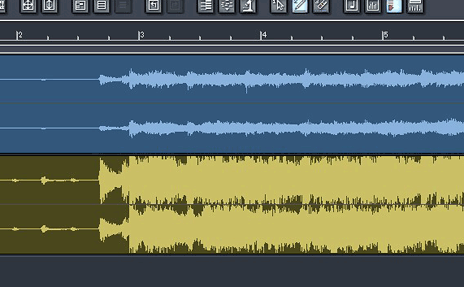インディアンフルートとバグパイプ-Enya China Roses
北米インディアンに伝わる笛と電子バグパイプでエンヤの『チャイナ・ローゼス』を演奏しました。笛の運指については動画を一時停止しながらご確認ください。
インディアンフルートについて
演奏したインディアンフルートはドレミフルートという、西洋音階に調律した特殊なフルートです。指穴が7つあります。China Rosesは易しい曲なのでふつうのインディアンフルート★1 でも演奏できると思いますが。西洋の曲を演奏するなら、当然のことながら、西洋のドレミ音階に調律している笛で演奏するのが楽ちんです。
それとこの曲は後半に半音だけ高い音に移調します。
なので後半はキーが半音高い笛に取り替えて吹きました。西洋のクラシック音楽では同じ笛でがんばって半音を吹くのが流儀ですが、民族音楽ではこのように、曲の調に合わせて笛を取り替えることをよくやります。運指はいつも同じなので楽ちんです。
» ドレミ音階のインディアンフルートについて
バグパイプについて
演奏したバグパイプはレッドパイプという、ドイツ製のエレクトリック・バグパイプです。
バグパイプの形をしたシンセサイザです。これはいちばんシンプルな形の初期モデルです。黒とオレンジのいかにも作り物っぽい革バッグに、メロディを演奏するチャンター管が付いているだけという。しかしそれがいい。元々はプライベートで練習するように購入したのですが、意外に見栄え良さそうなので、試しに使ってみました。
» レッドパイプについて
ユニゾンを積極的に試しています
このところずっとユニゾンを使いこなす練習をしています。
たくさんの音を使う豪華絢爛なポップス作品を製作するには、ユニゾンを使いこなすことが重要だと考えています。ユニゾンして楽器のメロディラインをまとめ減らさないと、ごちゃごちゃと何をやっているか分からない状況に陥るでしょう。
ユニゾンとは「音の性質の強化」だと、私は理解しています。
例えばたくさんの伴奏楽器が鳴っている中で、笛だけが主メロディを演奏すると聞こえにくいので、ピアノやチェロ★2 でユニゾンしてして主メロディを強化しました。
またチェロが少し弱かったので、要所要素でコントラバスでユニゾンして低音を強化しました。
また伴奏しているピアノのアルペジオをはっきり聞かせるために、ハープシコードでユニゾンしてピアノのメロディラインを強化しました。
ユニゾンした音は……聞き分けられないようにこっそり鳴らして下支えするやり方もありますが、豪華絢爛にするならむしろはっきり聞こえてほしいところです。なので、ユニゾンの音は1/16拍~1/8拍ほどテンポディレイで遅らせて鳴らしました。
CurveEQを使ってみました
マスタバスに差すイコライザとしていつものGlissEQと、今回は新しくCurveEQを併用しました。
CurveEQはイコライザなんですが、ある曲の周波数特性を他の曲にコピーするという特殊機能を持っています。平たく言うと自分の音楽作品の雰囲気を、他の曲の雰囲気にそっくりにすることができます。
今回は本物のエンヤのChina Rosesの雰囲気をコピーして私の作品にペーストしました。どうでしょう、エンヤっぽく聞こえますか?
CurveEQの、曲の雰囲気をコピー&ペーストするという機能はアイデアとしては秀逸ですが、実際には内容の伴わない不完全な機能です。使える・使えないでいえば、使えないエフェクタです。でも私はこれをお金を払って買いました。限定的にでも使える状況はないかと、けち臭く模索しているところです。GlissEQだって、最初は使えないアイデア倒れのエフェクタだと判定してしばらく捨ててましたからね。案外CurveEQだって使えるかもです。
» CurveEQについて
★ ふつうのインディアンフルート
初心者がいきなり吹いても美しい音で鳴ってくれる。適当に指を動かしても曲っぽく聞こえてくれる。インディアンフルートはまるで魔法みたいな笛ですが。
最大の短所として、ふつうの曲が吹けません。音階はドレミファソラシドが全部揃っていませんし、音域は1オクターブしかありませんし。確かにアメイジング・グレイスやもののけ姫など、インディアンフルートで吹ける有名な曲がいくつかあります。また換え指や半穴開けしてがんばれば、なんとかドレミファソラシドを鳴らすこともできます。しかしそれで「ふつうの曲も吹けます!」と宣伝するのはどうでしょうか……やればできるというのと実用的であるのは別だと思いますね。実用的でないところは実用的でないと、はっきりお客さんに伝えた上で買ってもらうべきだと思いますね。
★ チェロ
厳密にはチェロの音ではなくて、ビオラ・ダ・ガンバという中世の古楽器です。外観はチェロそっくりですが、ギターのようにネックにフレットが付いています。チェロが熟女のような艶めかしい音色であるのに対して、ビオラ・ダ・ガンバは老婆のようにしわがれた音色です。私はチェロの音源を持っていないので仕方なく使っていましたが、最近はビオラ・ダ・ガンバの音が好きになりました。
楽器があればもっと楽しい毎日
» 変わった楽器、珍しい楽器の販売は世界楽器てみる屋