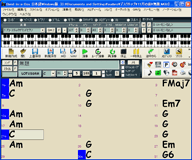BIABのオーディオコードウィザードのヒント 3
Band-in-a-Box(略してBIAB)は自動で楽器を伴奏してくれる便利なDAWです。楽器が弾けなくても打ちこみが苦手でも、音楽作品を作ることができます。オーディオコードウィザード(略してACW)はBIABの機能の一つです。mp3やwmaなど音楽ファイルを読みこんで、コード進行を逆算します。オリジナル曲の音さえあれば、コード進行を決めて伴奏をさせて、私だけのカバー曲を作ることができます。ここではACWの使い方について、そのヒントを挙げています。
苦手なことを無理強いしない
ACWにはコードを上手に逆算できるタイプの曲とできないタイプの曲があります。つまりACWには得意な曲と苦手な曲があります。そりゃそうだろうなという話です。ACWの苦手な曲が事前に分かっていれば、(この曲は絶対に正しく逆算できないな……)と憶測がつけば、最初から楽譜を探すとか、いっそ諦めて他の曲を採用するとか、とかく時間を無駄にせずにすむでしょう。
ACWの得意な曲
ACWが上手にコードを逆算できるタイプの曲というのはずばり、BIABが自動伴奏するような曲です。ドラムがズンタタと正確にリズムを叩き、ベースがボンボンとオーソドックスにコードのルート音を鳴らして、ピアノやギターがシャカシャカと細かいリズムを刻みながらセブンスやテンションなどを暗示する。そんな曲を上手にコード逆算できます。
テンポは、メトロノームで計ったように正確な方が無理なく逆算できます。
経験的に、3拍子や6拍子よりも4拍子の方が良く逆算できます。
拍子は3拍子でも6拍子でも4拍子でもなんでもとにかく、始めから終わりまでずっと同じで変わらない曲がいいです。
「ワン・ツー・スリー・フォー!」で始まるきっぱりした出だしの曲は、曲の頭を決めやすいです。
曲が途中で転調するのは……これは、逆算精度にはあまり関係ないです。そもそもACWは、曲が途中で転調したことを理解できないっぽいです。それどころか、その曲のキーはなにか?ということも実質は理解できてない印象です。(それこそ問題だとも言えます。)
ACWの苦手な曲
ACWが上手にコードを逆算できないタイプの曲、苦手な曲というのは、得意な曲の反対です。何よりもベースの演奏がオーソドックスであることが重要です。ベースが以下のような演奏をすると、逆算精度は極端に低下します。
- F/Gのようにベースがコードと関係ない音を弾く
- ベースがセブンスやテンションの音を弾く
- ベースがリードギター顔負けの複雑なフレーズを演奏する
- そもそもベースらしい音がない。マンドリンの甲高いシャカシャカした伴奏に合わせて歌うとか
とにかくトリッキーなベース演奏をものすごく嫌います。これに関してはユーザがほとんど補正できません。致命的です。同様の理由で、コード進行の概念がない種類の民族音楽や中世ヨーロッパの古楽なども正しくコードを逆算する事ができません。(ユーザとしては、こういう音楽こそまさにコード進行を提案してほしいのですが。)
メロディーだけの曲、アカペラの曲などは情報が少なすぎて正しく逆算できません。
3拍子や6拍子の曲は、4拍子の曲と比べて正しく逆算できないリスクが高いです。3拍子や6拍子はダメだ、ということではありません。むしろすんなり逆算できるケースの方が多いのですが。万が一うまくいかなかった場合に、いろいろと面倒なノウハウを駆使することになります。
途中で3拍子から4拍子に変わる、サビの前の一小節だけ一拍長く伸ばす、といった曲も面倒です。ACW自体には苦手意識はないのですが、ユーザがそれをACWに理解させるのに苦労します。そもそもBIABはそのような構造の曲を易しく扱える仕組みになっていませんし…
だんだん音が大きくなって曲が始まるフェードインの出だしは、曲の頭をどこにすればよいか悩みます。これはACWではなくユーザ側の問題ですけど。
まずはACWの得意な曲で練習
BIABの数ある機能の中でも、ACWは使いこなすのが難しい機能の筆頭です。「どうにもACWをうまく使いこなせない」という人は、自分の趣味はひとまず脇に置いて、ACWの得意な曲を使って練習してみてはいかがでしょうか。
- 4拍子であること
- テンポが正確(というか機械的)であること
- 「ワン・ツー・スリー・フォー!」で始まるきっぱりした出だしであること
- ベースの演奏がオーソドックスであること
- ベース、ドラム、キーボードにギターなど、一通りの楽器が使われていること
- 曲のジャンルは往年のポピュラーソングなどがお勧め
特に打ちこみで作ったMIDI演奏の曲はどこか機械くさいので、音声ファイルになっていてもACWで逆算しやすいです。YouTubeやニコニコ動画でそのような作品を探して使ってみてはどうでしょうか。
楽器があればもっと楽しい毎日
» 変わった楽器、珍しい楽器の販売は世界楽器てみる屋